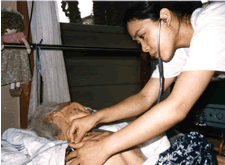Ⅰ なぜ、訪問看護をボランティアで・・・
1983年当時、慢性疾患の増加や医療の進歩に伴う救命率の向上により、医療器材・器具を装着したまま退院を余儀なくされる人々がますます増え、退院後のフォローが質・量ともに必要になっていた。
しかし、病院を基盤にした訪問看護は、地域に密着していない基幹病院としては難しく、赤字覚悟では始められなかったのか、全く動きはみられなかった。退院をせまられ、危機状況を抱える家族を目の前にして、放ってはおけないという人道的精神から発し、課外でボランティアというかたちででも、在宅看護活動を始めるしかなかったのであろう。仕事と家庭さらにボランティアをこなす活動は3年1ヶ月も続いた。
いつでも相談でき、困ったときにすぐ来て欲しいという看護のニーズに対して、提供する側も受ける側にも甘えが顔を出すボランティア。
家族の危機を目のあたりにして、ナースだからこそ放ってはおけなかった。「何とかしましょう」の一言は赤十字で人道・奉仕の教育を受けた純粋な精神から発せられたと考える。そして、創設者の村松の病院内でICU婦長として活躍した行動力と、看護教育者としてのあるべき姿を追求する精神がなければ誠意と情熱だけで応え続けることはできなかったと考える。
『この人「ボランティアから真剣勝負」 日本経済新聞1986年 5月28日 取材記事より一部抜粋
ボランティアではなぜ続かないのか
会社を旗揚げした村松は「看護婦が、病院を離れて訪問看護の組織を作るのは日本では初めて。前例がないのでじっくり腰を落ち着けて取り組み、社会的評価を受けるのを待つことにします」と控え目に語るが作家/遠藤周作氏を顧問に迎えるなど、新プロジェクトにかける意気は軒高。
現代の高度な医療技術は、多くの人の命を救ったけれど、ひとたび病院から出ると寝たきりの障害を抱えているような人は、現行の医療制度では十分な看護が受けられない。そのギャップを埋めるのが目的です。A
ボランティアの限界
3年前、看護婦仲間と訪問看護のボランティア活動を始めた。「でも、ボランティアだと疲れた日は休んでしまったり、つい甘えがでてしまう。看護を受ける側も遠慮がち。そこで有料サービスを始めようということになったのです」その話を村松さんが、たまたま遠藤氏に話した所「大いにやりなさい」資金を一部援助してくれる団体までさがしてくれた。
ただ、厚生省は「看護婦の職務は医師の指示のもとに診療の補助を行なうこと。看護婦だけが独立して訪問看護をすることには慎重さが望まれる」との見解をしめしている。
村松さんは「無論、医師の指導は受けます。だが、看護婦がこれからの社会で果たすことは医師の下働きをすることではない。医師と共に医療の両輪を支えることにある」と自論を展開する。』
時代のニーズに合わせた看護活動のパイオニアとしての出発は「この人、ボランティアから真剣勝負へ」の新聞記事に記されている。
アンダーラインAの内容にもあるような医療問題から目をそらさず、行動をおこしたのはナースとしての倫理観・正義感が極めて強かったからだと私は思う。そして、ボランティアとしての訪問看護は継続した体制、双方の意識という点などにおいて、3年1ヶ月体験した結果その限界を認識できた。と考えられる。
********************************************************************************************************
|
|
|
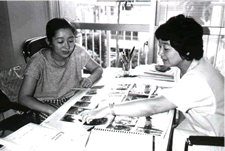 交通の至便な新宿区高田馬場の事務所を選ぶ。一人一人 のケースを検討し、より質の高い看護をめざしナース間 の連携を密にする。 |
Ⅰ なぜ、訪問看護をボランティアで・・・
Ⅱ 何もない。自分達で作るしかなかった。~ナース手作りの会社の誕生~
Ⅲ 活動を続けるための苦悩と決断 シルバー産業の嵐の中で・・・
Ⅳ ジャーナリストからいただいた「開業ナース」の命名 その1
ジャーナリストからいただいた「開業ナース」の命名 その2
Ⅴ 開業ナース 村松 静子
Ⅵ 村松静子を支えた3人の男たち
<戻る>